西尾の偉人(外山 滋比古)
外山 滋比古(とやま しげひこ)(1923年~2020年)
英文学者:知の巨人

西尾とのゆかり
幡豆郡寺津町生まれ(現 西尾市寺津町)
西尾尋常高等小学卒業(現 西尾小学校)
主な功績
日本の英文学者、言語学者、評論家。 著作は専門の英文学から言語学、子育て論、 ジャーナリズム論まで幅広く、 国語の教科書や各種入試問題の頻出著者としても有名。 お茶の水女子大学名誉教授。 昭和58年(1983年)の著書『思考の整理学』 は累計発行部数263万部以上。 2000年代にも東大生や京大生に一番読まれた本として話題となったロングセラーで、文庫版は126刷に達している。生涯で250冊以上を執筆。 平成5年(1993年)に「ふるさと西尾市民顕彰」受賞。
名言・考え
詰め込み型教育や知識の偏重から起こる弊害と、自分の頭で考える大切さを説いた。
異質な人と対話を!性格、考え方が反対の人と友だちになれ。
・人は人との交わりにおいて成長する。人にぶつかること。自分とさまざまな点で違う人と話をすると、まず、楽しい。気づかされることが多く、考えるようになる。アイデアが浮かぶ。浮かんできた言葉を書き留める。文系の人は理系の人と努めて友だちになるとよい。かつてのサロンのようにいろいろな人が集まって啓発しあえる場所に身を置くこと。似たもの同士では発展がない。
・思いつくためにはしゃべること。本を読んでいるだけでは良くない。
アイデアを時間をかけて温める
・眠っている時、夢を見ている時、歩いている時、アイデアが浮かぶ。すぐに書き留められるように枕元にも紙と鉛筆を置いておく。書き留められ、温められたアイデアは10年後かもしれないが形になる。
・とにかく書き出してみる。それを数日後など時間をおいて眺めてみること。
様々な分野の方々との談話会
・専門分野の異なる人が集まって、自分が研究していることを順番に話す。すると、今まで気づかなかったことに気づいたり、アイデアが沸いてきたりして、自分の研究が思わぬ方向に発展することがある。昔の人は「三人寄れば文殊の知恵」と言ったが、談話会の参加者は最低三人は必要だ。
「三上」と「三中」
・昔から良い考えが浮かぶのは「三上」といって、馬上、枕上、厠上の三つ。要するに馬の上、床の中、トイレの中ということだが、馬上はいまの時代でいえば通勤途中ということになる。
・「三中」の状態も思考の形成に役立つと思う。これは夢中、散歩中、入浴中である。人間はその気になればいたるところで学び、考えられるということだ。
私たちが本来持っている未来を切り開く能力「人間力」
・勉強をしたけどうまくいかない、就職もうまくいかない、生活が苦しい、思わしくないことが重なって本当に困った、何とかしてこれを乗り越えて負けずに生きていく。その時に「人間力」が出てくる。幸せで順調に生きている人は、成果はあげられても「人間力」はむしろ衰えていく。
・「人間力」を高めるには、何でもいいので、高い目標を作って、とにかく真剣になって努力する。失敗してもよい。目指そうとして努力をしていく、その過程に「人間力」というものが出てくる。自分が育んだ人間力は他人からもらった力とは違う。
名言
「誰かに引っ張られて飛ぶグライダー型ではなく、自分の頭で考え、自力で飛び回る飛行機型の人間こそ必要」
「アイデアを形にするには頭の中の醸造所で時間をかける… しばらく忘れるのである。”見つめるナベは煮えない”」
「常識はまず疑え」
【『思考の整理学』より】
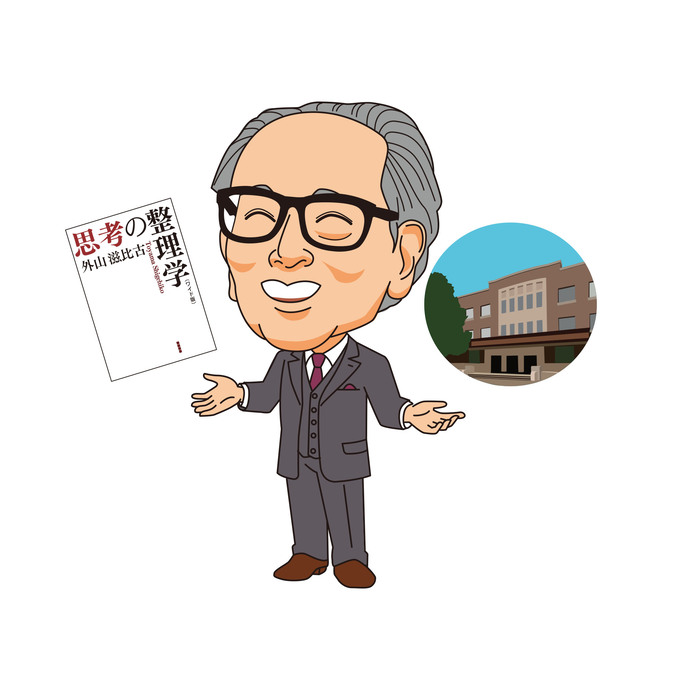
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書政策課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 秘書:0563-65-2171
- 企画政策・行政経営:0563-65-2154
- ファクス
- 0563-56-0212