お茶のお話2
元々はツバキ科のお茶の木、製法によっていろいろなお茶ができます。
お茶の種類はこんなにたくさん
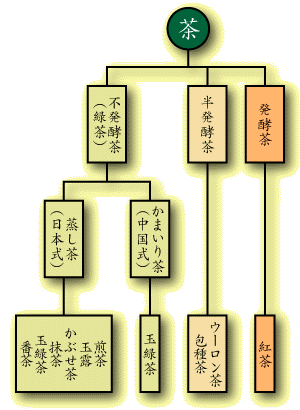
不発酵茶
鮮葉の酸化酵素の活動をできるだけ速く停止させるため、摘まれた葉は工場ですぐに蒸されたり、釜で煎られたりして熱を加えます。酸化を防いだ後、球状か針状に揉みながら乾燥します。
緑茶をつくるこの製法は、葉の成分を壊さないで閉じこめるため、紅茶やウーロン茶より数段健康によいといわれる最大の理由です。
発酵茶
不発酵茶とは反対に酸化させてつくるお茶。鮮葉を加熱しないでしおれさせ(萎凋)、揉みます。揉むことによって細胞は破壊され酸化が助長されます。酸化酵素の働きを止め、乾燥させるため最後に熱を加えます。この製法で香りを楽しむ紅茶がつくられます。
半発酵茶
日光と室内で徐々にしおれさせながら葉の水分を減らし、30パーセント程度酸化したところで加熱、酸化停止をします。発酵茶の紅茶のように紅くなるまで発酵させないウーロン茶がつくられます。
緑茶の種類
煎茶、番茶、茎茶、焙じ茶、粉茶、玉露、抹茶などなど、日本茶の種類は多種ですが、日本茶はほとんどのものが蒸製の緑茶です。茶色をした焙じ茶も立派な緑茶で、緑色の緑茶(煎茶や番茶)を強火で煎ったものなのです。
緑茶の種類
煎茶、番茶、茎茶、焙じ茶、粉茶、玉露、抹茶などなど、日本茶の種類は多種ですが、日本茶はほとんどのものが蒸製の緑茶です。茶色をした焙じ茶も立派な緑茶で、緑色の緑茶(煎茶や番茶)を強火で煎ったものなのです。
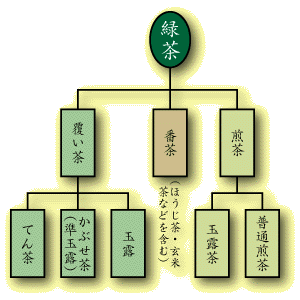
煎茶
茶葉を煎じ出して飲むことからこう呼ばれています。若葉の上部3から4葉が原料で、甘みと渋みが調和した爽やかな味で、日本で生産されているお茶の約80パーセントが煎茶です。
番茶(晩茶)
葉が硬くなってから摘んだもので、柔らかい茎、煎茶をつくる工程で除かれた大きな葉などを原料としています。香りが少なく、苦みや渋みがあり、さっぱりとした味です。下級煎茶を番茶と呼ぶ地域もあります。
覆い茶
新芽が伸び始めた頃、直射日光が当たらないよう茶園全体に覆いをして育てます。このためアミノ酸の一種で日本茶のうま味の元であるテアニン成分が増え、カフェインや葉緑素もたっぷり含まれています。甘くまろやかなうま味が特徴で、玉露やてん茶(抹茶の原料)になります。
その他お茶と呼ばれながら、お茶の葉を用いないをお茶を参考までにご紹介します。
麦茶・ハトムギ茶・アマチャヅル茶・甘茶・どくだみ茶・ルイボス茶・ハーブティなど
抹茶ってどんなもの?
よく知られているように茶道で用いられるお茶を抹茶といいます。新芽がふく4月上旬から茶園全体を人工的に覆い、葉を直射日光から遮って育てます。玉露などの高級茶をつくるときもこのように栽培します。なぜ太陽の直射を避けるのかというと、直射を遮ることにより、根から吸収した養分が葉の部分に多くたまり、緑茶だけが持つテアニンというアミノ酸の一種を増加させるからです。テアニンは昆布や化学調味料のうま味成分で、高級茶ほど多く含まれ、下級茶になるほど少なくなります。値段の高いお茶を飲んだときの独特のうま味がテアニンなのです。このように栽培されたお茶の葉を蒸し、揉まずに乾燥したものがてん茶です(玉露は蒸して揉みながら乾燥します)。このてん茶を石臼で細かな粉に挽いたものが抹茶です。西尾市はこのてん茶で日本有数の生産量を誇っています。
粉になったお茶の葉を丸ごと飲む抹茶は、うま味の成分のおいしさはもちろん、種々のビタミンやミネラル、繊維など体によい薬効成分を食べる感覚で取り入れることができます。普通の緑茶のようにお湯に煎じて飲むよりも効果は大きいといえるでしょう。
このページに関するお問い合わせ
交流共創部 観光文化振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 文化振興:0563-65-2197
- 観光:0563-65-2169
- ファクス
- 0563-57-1317
交流共創部観光文化振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
- 農政・水産:0563-65-2135
- 農政・林務:0563-65-2136
- ファクス
- 0563-57-1322