お茶のお話1
人類がお茶との最初の出逢いに求めたのは「薬」として
全国有数の生産地「西尾の抹茶」について徹底解明
お茶という言葉が登場したのは紀元前200の文献
紀元前200年頃、中国東漢時代に書かれた「神農本草」によれば、「3,000年以上の昔、神農(漢方医学の祖で古代中国の伝説神)が薬となる草根木皮を探し、薬効を確かめるために食し、毒にあたるとそのたびに茶を喫して解毒した」とあります。お茶は飲料として人々に愛されるよりずーっと以前は、薬として生の葉を噛み食べるものとして利用されていたようです。
飲まれるようになったのは3世紀頃、漢の時代。「広雅」という書には、団茶(茶の葉を固めてつくる)に熱湯を注いで飲んだと書かれていますが、やはり薬効を求めてのこと。
嗜好飲料としても扱われるようになるのは、三国時代です。盛んになった仏教が飲酒を禁じたことから、お茶が注目を集めるようになります。随の時代には上流、僧侶のものだったお茶が庶民にも広まり、唐の時代にはお茶を飲ます店もできました。その唐の時代の760年頃、お茶のバイブルとして生まれたのが、「茶は南方の嘉木なり」で始まる全三巻の「茶経」。これまで断片的にしか伝わっていなかったお茶の情報を集大成した専門書です。これを著した文人「陸羽」は現在も茶祖、茶聖として祀られています。
お茶の原産地はどこ
原産地はもちろん中国です。中国のどこかはいろいろな説がありますが、南西部の雲南地方から四川地方にかけての丘陵部が有力です。雲南省南部には、かつて栽培された茶の木が野生化し、樹齢1,000年を超えるものがあります。ここからアジアの温暖な地域、アジア照葉樹林帯であるインドのアッサム地方からタイ、ミャンマー北部の山岳地帯へ、中国南部から日本の西南部へ広がり、世界の東西各地へ広がっていったといわれています。そして広まった先々でその土地にあった品種に改良され種類も豊富になりましたが、もともとお茶の木は大別すると2つの系統に分けられています。葉に小さく丸みがある低木で寒さにも強いのが「中国種」で小葉種と呼ばれ、主に緑茶やウーロン茶用に栽培されています。もう一つは、葉は大きなものでは靴底ほどにもなり、野生では20から30メートルにもなる高木で寒さに弱い「アッサム種」です。これは大葉種といわれるものでインドやインドネシアなど、熱帯地方で紅茶用として栽培されています。また中国にはこの2種類の中間の大きさを持った品種が多く、これを「中国系アッサム種」、中葉種と呼ぶこともあります。さらに細かく「中国種・中国大葉種・シャン種・アッサム種」とする場合もあります。
現在お茶が栽培されているのは世界で30か国余り、南緯38度から北緯45度、東経150度から西経60度の範囲に及んでいます。
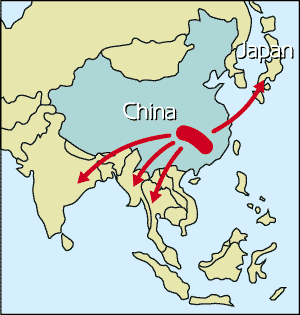
日本人とお茶との出逢い
日本にお茶がもたらされたのは、遣唐使として唐に留学した僧侶たちが持ち帰ったのが始まりです。最初に記録に表れるのは平安初期の「日本後記」です。入唐僧の一人、近江梵釈寺の大僧正永忠が帰国後の815年、嵯峨天皇を自寺に招き、お茶を煎じ献じたとあります。飲み方はおそらく、団茶(茶の葉を固めてつくる)を削り荒い粉にし、お湯に入れ煎じて飲んだと考えられます。長い船旅で持ち運びに便利なものは団茶であっただろうと推測されるからです。最新の唐風文化である喫茶のたしなみは、当時の知識人の間で流行したらしく、上流階級の儀式や行事に用いられるものとして、嵯峨天皇はお茶の栽培や製茶を命じていたようです。
日常的にお茶が飲まれるようになるのは鎌倉時代になってから。中国の宋に留学した僧、栄西は2度目の留学を終え1191年、多くの教典、臨済宗の教えとともに宋の新しい茶種と抹茶法という飲み方を持ち帰りました。栄西はお茶の栽培を普及させ、お茶を長寿の薬として勧める「喫茶養生記」を著しました。ここから日本の喫茶文化がスタートしたといわれる書です。栄西のもたらした抹茶法とは、今日の茶の湯の原型ともいえるもので、茶碗の中に挽いたお茶の粉を入れ、お湯を注ぎ茶筅でかき混ぜるという薄茶に近いものでした。
日本にお茶が深く根付くために重要な役割をした、もう一人の人物がいます。栄西から茶種を贈られた、栂尾高山寺の僧、明恵です。禅宗の布教に励と同時に、全国に茶を広めていくことにより、栽培も盛んになり、貴族や僧侶たちの儀式や薬用であったお茶は、次第に嗜好飲料になっていきました。
このページに関するお問い合わせ
交流共創部 観光文化振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 文化振興:0563-65-2197
- 観光:0563-65-2169
- ファクス
- 0563-57-1317
交流共創部観光文化振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
- 農政・水産:0563-65-2135
- 農政・林務:0563-65-2136
- ファクス
- 0563-57-1322